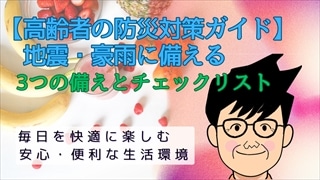高齢者の防災対策、なぜ今すぐ始めるべき?
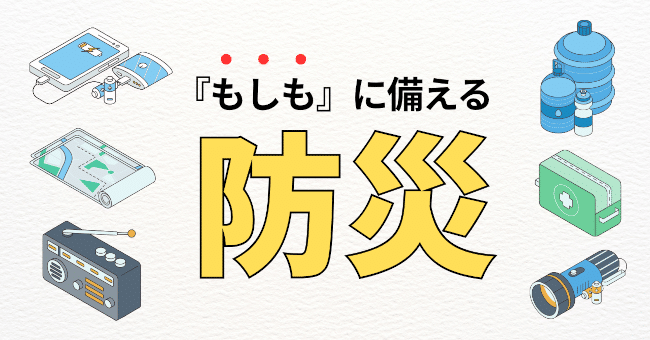
◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。
にほんブログ村 |
シニアライフランキング |
日本は、地震や豪雨といった自然災害が多く、高齢化も急速に進んでいます。もしもの災害時に、「自分の命は自分で守る」という意識を持つことは、自分だけでなく、家族や周囲の人々の負担を減らすことにもつながります。
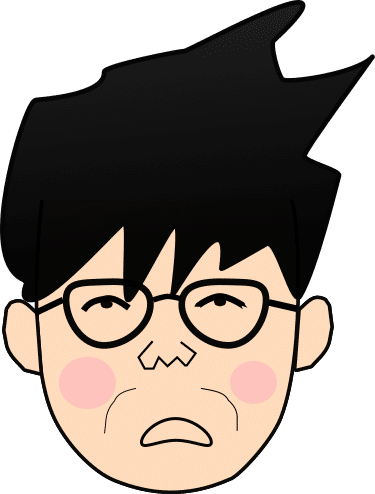
「最近、地震や豪雨のニュースを見るたびに、もしものことがあったらどうしよう…」と不安に感じていませんか?特に、体力に自信のない高齢者の方は、防災対策をどうすればいいのか悩んでしまうことも多いでしょう。
でも、ご安心ください。この記事では、あなたの不安を少しでも和らげ、安心して過ごせるための具体的な備え方をわかりやすく解説します。実際に、2018年の西日本豪雨では、避難所生活が原因で病状が悪化した80代女性の例もあります。

このような事態を避けるためにも、日頃からの対策が不可欠です。今すぐできることから、一緒に始めてみましょう。
高齢者が直面する災害時の3つの課題
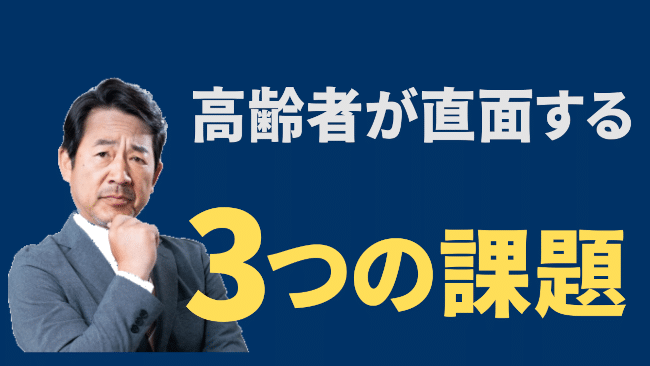
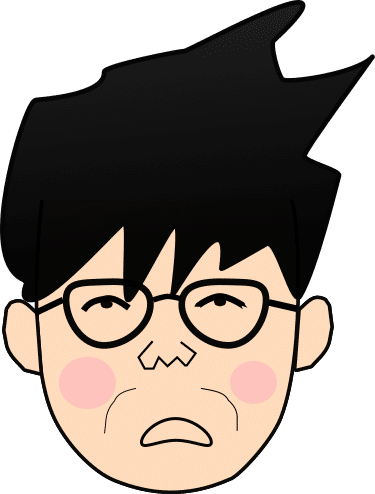
災害時、高齢者は「災害弱者(災害時要援護者)」と言われることがあります。
これには、主に3つの理由があります。
1. 避難が困難 急な揺れや、浸水、土砂崩れから逃れるには、素早い避難が必要です。しかし、足腰が弱くなったり、持病があったりすると、スムーズに避難するのが難しくなります。夜間であれば、暗闇の中を歩く危険性も高まります。
2. 避難所での体調悪化 避難所は多くの人が集まるため、ストレスや感染症のリスクが高まります。特に、慣れない環境での集団生活は、持病が悪化したり、いわゆる「エコノミークラス症候群」になったりする危険性があります。エコノミークラス症候群とは、長時間同じ姿勢でいることで血行が悪くなり、足などにできた血の塊が肺の血管を詰まらせてしまう病気です。
3. 備蓄品の選択が難しい 災害時の備えとして、食料や水は重要です。しかし、高齢者の場合は、入れ歯や補聴器、持病の薬など、日頃から使っているものがなければ命に関わることもあります。一般的な防災セットだけでは不十分な場合が多いのです。
これらの課題を乗り越え、命を守るためには、事前の備えが何よりも重要です。
今すぐできる!高齢者のための防災対策チェックリスト
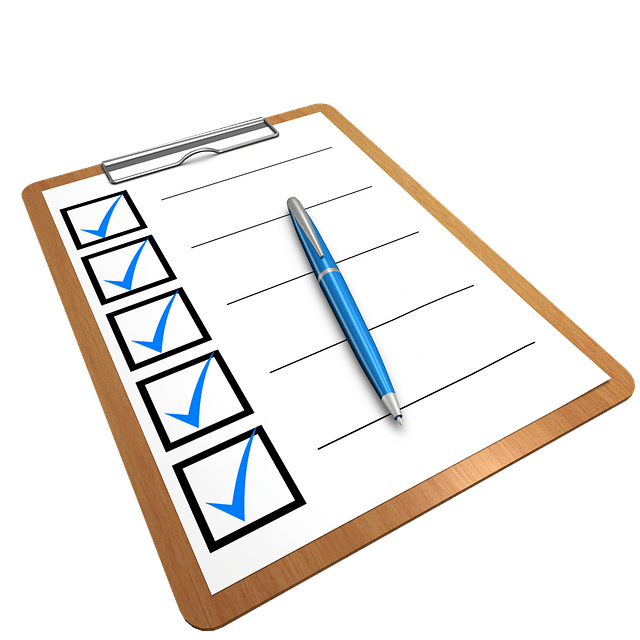

災害に備えるための具体的なチェックリストをご紹介します。ご家族と一緒に確認しながら進めることをおすすめします。
備え1:身体状況に合わせた防災グッズの準備と医療情報の管理
高齢者の防災グッズは、単なる備えではなく、命を守る道具です。身体の弱さを補い、負担を軽減できるよう、軽量で使いやすく、安全性を意識したアイテムを選びましょう。
1. 医療品の準備と管理 多くの高齢者は高血圧や糖尿病などの持病があり、定期的な薬の摂取が必要です。災害時には医療機関が混乱し、薬の供給が滞る可能性があるため、最低でも1週間分の常備薬を準備しておきましょう。
また、お薬手帳のコピーやアレルギー情報、かかりつけ医の情報を記した医療情報カードを常に携帯することで、医療スタッフが迅速に対応できるようになります。
2. 身体的負担の軽減と快適性の確保 避難所の硬い床での生活は、腰痛や関節痛の原因となることがあります。軽量な折りたたみ椅子やクッションを用意し、身体への負担を軽減しましょう。
また、体温を逃がさないための防寒対策として、軽量で収納しやすいアルミブランケットは必須です。避難所の冷える床に敷くなど、体に巻きつける以外の使い方もできます。
備え2:適切な避難方法の検討と情報収集
高齢者の避難は、選択肢を理解し、事前に計画を立てることが重要です。
1. ハザードマップと避難経路の確認 お住まいの地域のハザードマップ(自然災害による被害を予測し、避難場所などを示した地図)を確認しましょう。これにより、自宅周辺の土砂災害や浸水などの危険度や、避難所までの安全なルートを知ることができます。
運動不足解消も兼ねて、日頃から散歩がてら近所の避難場所への道順を複数確認しておくと良いでしょう。
2. 「在宅避難」と「福祉避難所」の選択肢 避難所での過酷な生活は、体調悪化や認知症の症状悪化につながるリスクがあります。自宅に大きな被害がなかった場合は、安心できる環境で在宅避難を続けることも一つの選択肢です。そのためには、非常用トイレや入れ歯などの備蓄品を自宅に備えておく必要があります。
また、持病のある方や介護が必要な方が優先的に利用できる「福祉避難所」を事前に確認しておくことも重要です。2021年のガイドライン改訂により、支援や介護が必要な方は、指定された福祉避難所へ直接避難できる仕組みに変わりました。
備え3:地域との連携と「助けてもらう力(受援力)」の強化
災害時には、一人で全てを解決しようとせず、地域との連携や「助けてもらう力(受援力)」を強化することが命を守る上で非常に重要です。
1. 「受援力」の重要性 助けを求めることを恥ずかしいと感じる高齢者の方もいますが、災害時は近所の人などと協力し合える関係が命を守ります。普段から近隣住民とのコミュニケーションをとり、いざという時に助け合える関係を築いておくことが大切です。
2. 「避難行動要支援者名簿」への登録 市町村は、災害時に自力での避難が難しい方を記載した「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられています。65歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の高齢者のみの世帯の方などが対象です。
この名簿は、本人の同意を得て、事前に支援関係者(支援者)に提供されることが可能です。ご自身が対象となる場合は、名簿への登録を検討し、必要な支援を受けられるよう準備しておきましょう。
3. 家族との安否確認方法の共有 日頃から離れて暮らしている家族とは、災害時の連絡ルールを事前に決めておくことが非常に重要です。災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板、無料Wi-Fiを使ったSNSなど、通信手段が混乱しても安否を確認できる方法を話し合っておきましょう。また、スマートフォンの連絡先を紙のメモに控えておくことも有効です。
高齢者の防災リュック、これだけは入れておきたい

高齢者の防災リュックは、通常の防災セットに加えて、個別の健康状態や生活習慣に合わせたものを用意することが重要です。
必須の防災グッズリスト
- 食べ慣れた食品と水分: レトルトのおかゆやゼリー飲料など、食べ慣れたものや、かみやすいものがおすすめです。
- 持病の薬とお薬手帳のコピー: 最低1週間分は薬を用意し、お薬手帳のコピーを必ず入れましょう。
- 衛生用品: 持病で紙おむつが必要な方は多めに用意し、ウェットティッシュや入れ歯洗浄剤も役立ちます。
- 現金: お店が開いてもカード払いができない場合があるため、小銭や紙幣(特に100円、10円、500円玉)を用意しておきましょう。
情報収集・連絡のためのアイテム
- 携帯ラジオ: 電池式のラジオを用意し、災害情報や避難情報を確認できるようにしておきましょう。
- スマートフォン&モバイルバッテリー: スマートフォンは情報収集や安否確認に役立ちますが、停電時には使えなくなります。ソーラー充電が可能なモバイルバッテリーがあれば、電気がなくても携帯電話などの充電が可能です。
- 身元情報・連絡先メモ: 自分の名前や住所、家族の電話番号を記載したメモを携帯しておくと、迅速な対応が可能になります。
意外と忘れがちな便利グッズ
- 入れ歯、補聴器、老眼鏡: 日頃から使っているものは、すぐに持ち出せる場所にまとめておきましょう。
- 軽量な折りたたみ椅子: 避難所の硬い床での生活で、身体への負担を軽減します。
- 懐中電灯(ヘッドライトが便利): 夜間や暗い場所での移動に必須です。
- 雨具(ポンチョや山登り用雨具): 避難時の濡れ対策として重要です。
- ホイッスル: 助けを呼ぶ際に役立ちます。
- 携帯用簡易トイレ: トイレに行きにくい避難所で、体調悪化のリスクを減らしてくれます。
最後に:今日から始める防災の一歩!
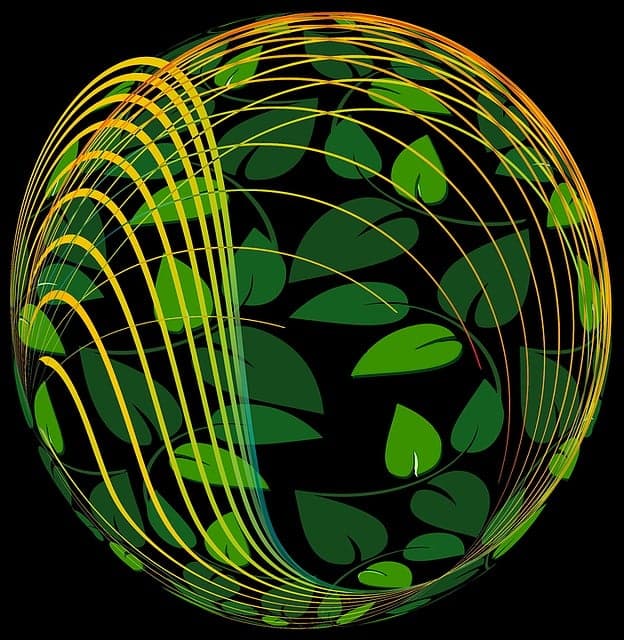
今回ご紹介したチェックリストを参考に、できることから少しずつ始めてみてください。防災グッズの備えだけでなく、日頃から災害への意識を持ち、自宅の安全対策や避難経路の確認、備蓄品の定期的な確認なども重要です。
「備えあれば憂いなし」という言葉があるように、災害に備えることは、あなた自身の安心につながります。この記事を家族や大切な人と共有し、一緒に防災について話し合ってみるのも良いですね。

いざという時にも「自分らしい生活」を続けられるよう、万全の準備を整えておきましょう。
【参考・根拠サイト】
- 内閣府防災情報のページ: 防災に関する基本的な情報や、避難行動要支援者名簿に関する詳細が掲載されています。
- 厚生労働省: 災害時の福祉避難所や、避難所での健康管理に関するガイドラインが提供されています。
- 気象庁: ハザードマップや災害情報に関する詳しいデータを確認できます。
- 日本赤十字社: 災害時の救護活動や健康管理に関する情報が掲載されています。