飼い主の「もしも」に備える、大切な家族との最善の別れ方

◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。
にほんブログ村 |
シニアライフランキング |
「この子と、もしも別れる日が来たら……」。そう考えると、胸が締め付けられる思いがしますよね。特に、ご自身の健康や将来に不安を感じる高齢者の方にとって、大切な家族であるペットの行く末は、避けては通れない大きな悩みかもしれません。
この記事は、そんなあなたの不安に寄り添い、ペットが最期まで幸せに過ごせるための引き取り先の探し方や、事前準備について、分かりやすく解説します。
この記事で解決できること

- 高齢者がペットを手放す具体的な理由(病気、施設入居など)と、その深刻な実態が分かります。
- 信頼できる引き取り先候補(民間団体、行政、個人)を比較し、それぞれのメリット・デメリットを理解できます。
- 引き取りにかかる費用相場や、費用を抑える具体的な方法が分かります。
- ペット信託や終生預かり制度など、将来の「もしも」に備えるための対策を学べます。
- 実際に引き取りを経験した人の声から、後悔しないためのコツを知ることができます。
なぜ、高齢者はペットを手放すのか?3つの深刻な理由

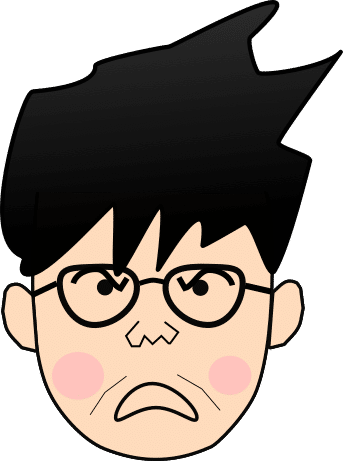
長年連れ添った大切な家族を手放すという決断は、決して簡単なことではありません。そこには、飼い主自身の深い愛情と、複雑な社会的な背景が絡み合っています。
1. 飼い主の病気や体力低下
最も一般的な理由が、飼い主自身の健康問題です。 これまで当たり前にできていたペットの世話が、加齢に伴う体力低下や病気によって困難になることは珍しくありません。
- 毎日の散歩が困難に: 足腰の痛みや心臓の持病で、犬の散歩が辛くなる。散歩はペットの健康維持に欠かせないため、飼い主の責任感と葛藤が生じます。
- 日常のケアが負担に: 猫のトイレ掃除や食事の準備、ブラッシングなどが、腕や肩の不調、視力低下で難しくなることがあります。
- 認知症によるリスク: 認知症を発症すると、ペットの世話を忘れたり、危険な状態に気づけなかったりするリスクも無視できません。
これらの問題は、単なる「世話が大変」というレベルを超え、「このまま飼い続けることは、ペットにとって本当に幸せなのだろうか?」という苦渋の問いを飼い主に突きつけます。
2. 施設入居・入院とペットの問題
介護施設への入居や長期入院も、ペットを手放す大きな理由です。 日本の多くの介護施設や病院では、衛生上の問題や他の入居者への配慮から、残念ながらペットの同伴が認められていません。
病状の悪化で緊急入院が必要になったり、自宅での生活が困難になり介護付き老人ホームへの入居を決断したりした場合、ペットの行き場がなくなってしまいます。家族や親族の協力が得られないケースも多く、飼い主は愛するペットと離れ離れになるという、想像を絶する悲しみに直面します。
中には、ペットを手放したくない一心で、施設への入居や治療をためらう人もいます。しかし、飼い主自身の健康と安全を考えると、入院や施設入居は避けて通れない選択となることがあります。
3. 経済的な理由と多頭飼育の破綻
年金収入が主な生活費となる高齢者にとって、ペットにかかる費用は大きな負担となり得ます。
- 医療費の急増: ペットも高齢になると、人間と同じように持病を抱えたり、特別なケアが必要になったりします。高額な手術や長期治療が必要になった場合、貯金が少ない高齢者にとって、費用を捻出することは極めて困難です。
- 多頭飼育の負担: 複数のペットを飼う多頭飼育は、費用だけでなく、体力や気力の面でも負担が大きくなります。全てのペットの世話を適切に行うことが難しくなり、飼育環境が破綻してしまうケースも少なくありません。
「自分がこの子たちを幸せにできないのであれば、もっと良い環境で暮らせる場所を見つけてあげたい」という、深い愛情ゆえの苦渋の決断が、ここにはあります。
高齢者とペットの「老老介護」問題|深刻な実態と社会課題

高齢者がペットを手放す背景には、日本の高齢化社会に伴う複雑な問題が潜んでいます。飼い主とペット双方が高齢になる「老老介護」が増加しており、飼い主の死亡や孤独死、認知症による飼育放棄といった事例が報告されています。
ペットも人間と同じように年を重ね、寝たきりになったり、認知機能が低下したりすることがあります。寝たきりの犬のおむつ替えや食事の介助、夜鳴きが激しくなった猫への対応など、ペットの介護は飼い主の体力だけでなく、精神的な負担も非常に大きいものです。特に、飼い主自身も高齢である場合、両立は困難を極めます。多くの飼い主は「自分がこの子の最期まで看てあげることができないかもしれない」という不安を抱き、「専門的なケアを受けられる場所を見つけてあげたい」と考えるようになります。
東海テレビ 特集記事で、東京都のデータで、飼育放棄した飼い主の約8割が高齢者であり、その主な理由として飼い主の病気、死亡、経済的理由が挙げられています。

また、行政の「殺処分ゼロ」政策の裏側で、保健所でのペットの引き取り拒否が増え、結果としてペットが外に遺棄されるケースも増加しています。これは動物愛護法違反であり、罰金刑の対象です。これらの問題は、単に個人の問題ではなく、社会全体で取り組むべき深刻な課題といえるでしょう。
あなたのペットを引き取ってくれる場所は?【引き取り先・預け先候補】

1. 【民間】専門の引き取りサービス・NPO法人
動物の保護活動を専門に行うNPO法人や民間団体は、ペットの命を第一に考え、手厚い保護とケアを提供してくれます。
代表的な団体には、認定NPO法人 人と動物の共生センターなどがあります。

- メリット
- 手厚いケア: 健康診断や不妊・去勢手術、社会化トレーニングなど、新しい飼い主が見つかるまでの間、適切なケアをしてくれます。
- 高い譲渡成功率: 厳格な審査で、ペットの性格に合った新しい飼い主を探してくれます。
- 相談体制の充実: 飼い主の気持ちに寄り添い、心のケアも含めてサポートしてくれます。
- デメリット
- 費用がかかる: 寄付金という名目で、数万円から数十万円の費用が必要になる場合があります。
- 受け入れ数に限りがある: 常に満杯で、すぐに引き取ってもらえない場合もあります。
2. 【行政】保健所・動物愛護センター
都道府県や市町村が運営する行政機関も、ペットの引き取り先となります。
- メリット
- 費用が安価: 手数料が数百円から数千円と、民間のサービスに比べて格段に安く済みます。
- 公的機関としての信頼性: 法律に基づいた手続きで、安心して進められます。
- デメリット
- 殺処分のリスク: 一定期間内に新しい飼い主が見つからなければ、殺処分される可能性があります。特に、老犬・老猫や病気を抱えたペットは、そのリスクが高まります。
- 引き取り後の追跡調査がない: 引き取られたペットがどうなったか、飼い主が知ることはできません。
安価であることだけで選択するのではなく、他の選択肢がすべて尽きた場合の「最終手段」として考えるべきでしょう。
3. 【個人】親族や知人、里親募集サイト
親族や知人、またはインターネット上の里親募集サイトを通じて、新しい飼い主を探す方法も有効です。
- メリット
- 慣れた環境に近い形で生活できる: 親族や知人であれば、ペットが安心して新しい生活を始められます。
- 自分で里親を選べる: 里親募集サイトでは、多くの希望者の中から、ペットに最適な人を探すことができます。
- 費用を抑えられる: 個人的なやり取りのため、高額な仲介手数料はかかりません。
- デメリット
- トラブルのリスク: 特に里親募集サイトでは、相手の身元が不確かで、後でトラブルになる可能性があります。悪質な人物も存在するため、慎重な対応が求められます。
- 相手に負担をかける可能性: 親族や知人に頼む場合、金銭的な援助や世話のサポート体制について事前に話し合う必要があります。
ペット引き取りにかかる費用相場と費用を抑える方法

ペットの引き取りにかかる費用は、選択するサービスによって大きく異なります。
1. サービスごとの費用内訳
- 民間の専門サービス・NPO法人: 数万円~数十万円。引き取り後の医療費、食費、人件費、活動費などが含まれます。
- 行政(保健所など): 数百円~数千円。事務手続きにかかる手数料が主な内訳です。
- 個人(親族・知人、里親募集サイト): 原則として費用はかかりません。ただし、これまでの医療費や飼育費用の一部を負担するケースもあります。
2. 費用を抑える3つの方法
- 複数の団体に相談する: 民間の団体によって費用設定は様々です。複数の団体に連絡し、比較検討しましょう。
- 里親募集サイトを積極的に活用する: 利用料が無料であるため、費用を抑えたい場合に有効です。
- 不妊・去勢手術やワクチン接種を済ませておく: 事前に済ませておくことで、団体に引き取ってもらう際の費用を抑えられる場合があります。
ペットの将来に備える2つの対策|後悔しないための準備

大切なペットの「もしも」に備えるための具体的な対策は、飼い主自身の安心にも繋がります。
1. ペット信託・ペット後見人制度
飼い主の死後や病気で世話ができなくなった場合に備え、ペットの飼育に必要な費用を信託財産として預け、新しい飼い主に渡してもらう仕組みです。
- ペット信託: 財産管理の専門家が、ペットの世話に必要な費用を新しい飼い主に定期的に渡します。
- ペット後見人制度: 事前に指定したペット後見人が、飼い主が不在となった後もペットの世話を引き継ぎます。
これらの制度を利用することで、ペットの生涯にわたる安心を法的に確保できます。
2. 終生預かり制度の活用
飼い主が病気や高齢で世話ができなくなった際に、特定の施設や団体にペットを預け、生涯にわたって面倒を見てもらう制度です。
- メリット: 専門家による安心のケアが受けられ、飼い主が急に入院や施設に入所した場合でも対応できます。
- デメリット: 高額な費用がかかることが一般的で、受け入れられるペットに条件がある場合もあります。
【体験談】ペットを引き取ってもらうまでの流れと後悔しないためのコツ

1. スムーズな手続きの進め方
ペットの引き取りを検討する際、まずは信頼できるNPO法人などに相談しましょう。電話でペットの年齢や性格、引き取り理由を正直に話すことが大切です。
その後、団体の担当者と面談し、ペットを連れていきます。この時、健康診断書やワクチン接種証明書など、事前に書類を準備しておくと手続きがスムーズに進みます。 引き取りが決まったら、費用や引き取り日について話し合い、手続きは完了です。
スムーズな手続きのコツは、「早めの相談」と「正直な情報提供」、そして「必要書類の準備」です。
2. ペットが新しい環境に馴染めるようにする工夫
大切なペットと別れる決断は辛いものですが、新しい環境にスムーズに馴染めるよう、飼い主がサポートしてあげられることはたくさんあります。
- ペットの情報を詳細に伝える: 性格、好きなこと、嫌いなこと、食事の好みなど、些細な情報でも新しい飼い主にとって大きな助けになります。
- 匂いのついたものを渡す: 普段使っていた毛布やおもちゃを渡すことで、ペットは新しい環境での不安を和らげることができます。
- 引き渡し後は、安易に連絡を取らない: ペットが新しい環境に慣れるまでは、頻繁な連絡は控えましょう。
まとめ:大切なペットの命を最期まで守るために

本記事では、高齢者が大切なペットを手放さざるを得ない様々な理由から、具体的な引き取り先、費用、そして将来に備えるための対策まで、幅広く解説しました。
大切なのは、これらの問題に直面する前に、ペットの将来について真剣に考え、備えておくことです。ペット信託や終生預かり制度の利用を検討したり、信頼できる相談窓口を見つけておくことは、飼い主自身の安心にも繋がります。

愛するペットの命を最期まで守るために、そして飼い主自身が後悔しないために、今できることから一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。


