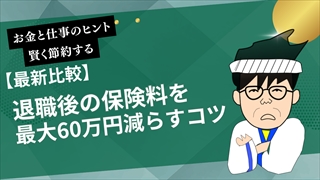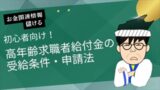はじめに
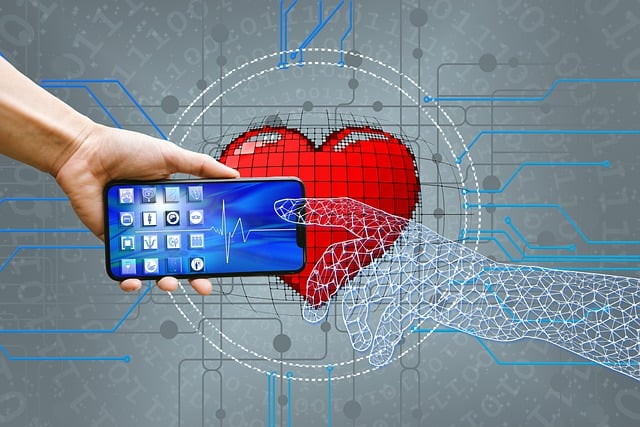
退職後の保険料で損したくない60代の方へ! 難しい「国保」と「任意継続」の比較を、プロではないあなたでもわかるように解説します。

年間最大数十万円トクする判断基準と、絶対に忘れてはいけない期限をチェックしましょう!
結論! あなたの状況別「最適な選び方」

年金生活を目前にした今、「保険料のムダな出費」は一番避けたいですよね。会社を辞めた後の健康保険の選び方(国民健康保険:国保か、健康保険任意継続か)は、「年に数十万円も差が出る」大切な家計の作戦です。
実は私もこの比較をしっかり調べた結果、任意継続を選び、年間18万円の節約に成功しました。(※この金額は、当時の私の所得と家族構成に基づく一例です。)
「結局、どっちを選べばいいの?」という疑問に、あなたの状況に合わせた最適な答えを、すぐに使える結論からお伝えします。
| あなたの状況 | 最も有利な選択肢 | なぜトクするのか?(判断の決め手) |
| 退職時の月給が高い + ご家族(配偶者など)を扶養に入れている | 健康保険任意継続 | 保険料に「上限」があり、扶養家族の保険料が無料になるため。 |
| 退職時の月給が低い または お一人で加入する | 国民健康保険(国保) | 前年の所得に応じて、保険料が安くなる制度が使える可能性があるため。 |
| 会社都合や倒産で退職した(自分から辞めていない) | 国民健康保険(国保) | 特別な保険料の割引(軽減)制度が使えるため。(後で詳しく説明します) |
この結論をもとに、あなたが年間数十万円トクするための、具体的な「金額の差」と「手続きのコツ」を今から解説します。
【金額の差】年収別!「任意継続」と「国保」どっちが高いか?
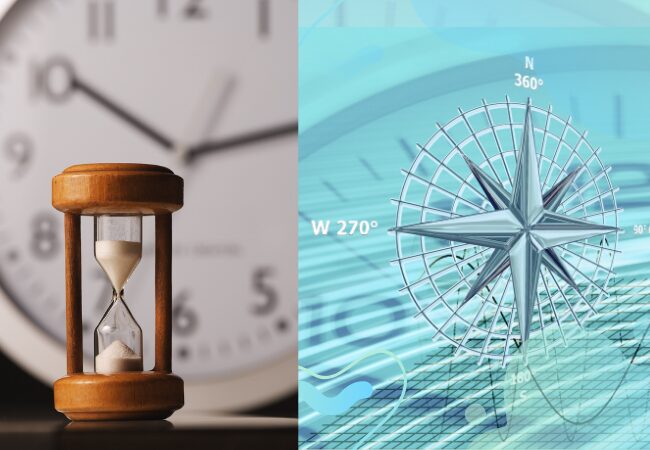
読者が最も知りたい「具体的な金額の差」を、わかりやすい表で見てみましょう。以下の表は、ご家族1名を扶養に入れている場合の、年間の保険料の目安です。
| 退職時の年収(目安) | 任意継続の年間保険料 (目安) | 国保の年間保険料 (目安・家族の分も含む) | 年間のおおよその差額 |
| 300万円 | 約36.8万円 | 約45.0万円 | 約8.2万円 |
| 500万円 | 約47.4万円 (※上限があります) | 約76.0万円 | 約28.6万円 |
| 900万円 | 約47.4万円 (※上限があります) | 約105.0万円 | 約57.6万円 |
【根拠・参考】 任意継続の保険料算定のベースとなる健康保険の標準報酬月額上限(令和7年度は32万円)および保険料率については、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式情報をご参照ください。 (例:令和7年度 協会けんぽ任意継続保険料額表)
なぜ、給料が高い人ほど「任意継続」が得になるのか?

これは、「保険料を決めるルールの違い」によります。
任意継続が安い理由:
- 保険料に「ストッパー(上限)」がある: 保険料を計算する元になる給料の額に、上限が設定されています。そのため、給料が高かった人ほど、この上限で保険料が頭打ちになり、お得になります。
- 扶養家族は無料: ご家族を扶養に入れる場合、その分の保険料はタダです。
根拠・参考】 任意継続の資格要件や扶養に関する詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続の加入条件に関する公式情報をご確認ください。
国保が高くなる理由:
- 上限がゆるい: 前年の所得に応じて保険料が高くなりますが、任意継続のような大きなストッパーがありません。
- 家族の人数分かかる: 扶養の考え方がないため、ご家族も国保に加入すると、全員分の保険料が必要になります。
【落とし穴注意!】任意継続の「たった一つの期限」
任意継続は、誰もがいつでも入れるわけではありません。特に、「申請の期限」を過ぎてしまうと、原則として加入できなくなり、国保を選ぶしかなくなります。
【絶対に忘れないで!】申請期限のチェックリスト
| 必要なこと | いつまでに? |
| 以前の会社の健康保険に加入していた期間 | 会社を辞める前日までに、2ヶ月以上続けて加入していること。 |
| 任意継続の申請手続き | 会社を辞めた日の次の日から20日以内に手続きをすること。 |
※20日を過ぎると、もう入れません!
お住まいの地域を管轄する協会けんぽ支部か、以前加入していた健康保険組合に、退職後すぐに連絡することが大切です。
【根拠・参考】 任意継続の資格取得要件(2ヶ月以上の加入期間、20日以内の申請)の詳細は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式情報にて必ずご確認ください。)
途中でやめたくなったら?(出口戦略)
任意継続は原則2年間ですが、途中でやめることも柔軟にできるようになりました。
- 保険料を払うのを忘れたとき(自動的に資格がなくなります)
- 再就職して、別の会社の健康保険に入ったとき
- 「自己都合でやめたい」とき: 2022年1月の法改正で、健康保険組合のルールによっては、いつでもやめることが可能になりました。

この法改正のおかげで、「とりあえず任意継続に入って、1年後に国保と比べて安かったら切り替えよう」という柔軟な選択ができるようになっています。
ちなみに、この切り替えるかどうがの選択の手順については、以下を参考にしてください。
- 切り替えたい年の3月に、住んでいる自治体で、新しい国民健康保険料の金額(4月から翌年3月までの金額)を確認。
- 1と、現在支払っている任意継続保険料を比較。
- 任意継続保険料が国民健康保険料より高く不利なら、加入している健康保険組合に※「任意継続の資格喪失届」を提出し、任意継続を打ち切る。
- 打ち切り希望月は、個人では指定できません。健康保険組合で資格喪失届を受理した日の翌月から打ち切りとなります。その為、提出は新しい国民健康保険料との比較が出来た3月に行い、翌月の4月1日で切り替えるのがベストです。この時、国民健康保険も、4月1日から始められるよう、自治体で手続きを行うことを忘れないようにしましょう。
【裏ワザ】国保が大幅に安くなる「特別な割引制度」

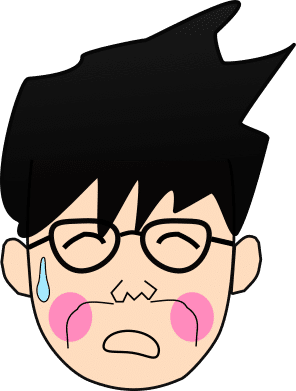
保険料が高くなりがちな国保ですが、退職の理由によっては、保険料が半分以下になる特別な割引制度(軽減特例)があります。
会社都合などで辞めた人への軽減特例
退職理由が「会社が倒産した」「会社から解雇された」など、あなた自身の都合ではない理由で仕事を失った場合、この制度が使えます。
| 割引の内容 | 適用期間 |
| 保険料の計算 | 前年の給与所得を「100分の30」として計算します。(例:給料が500万円だった人も、150万円として計算されます) |
| 適用期間 | 会社を辞めた日の次の日から次の年度末まで |
この割引が適用されれば、給料が高かった人でも、国保の方が任意継続よりグッと安くなる可能性が出てきます。
【根拠・参考】 国民健康保険料の軽減特例(非自発的失業者に係る軽減制度)は、厚生労働省の制度趣旨に基づき各自治体で実施されています。お住まいの市区町村の公式ホームページで「国民健康保険 軽減特例」と検索し、適用条件と具体的な軽減内容をご確認ください。(例:松山市公式HP )の公式情報で、適用条件と具体的な軽減内容をご確認ください。
必ず、お住まいの市区町村の役場窓口で「雇用保険受給資格証」(失業保険を受け取るための書類)を見せて、「保険料の軽減特例を使いたい」と相談してください。
迷わない!手続きの流れと必要書類

最終的にどちらの保険を選ぶにしても、「どこで、何が必要か」を事前に知っておけば安心です。
【パターンA】任意継続を選ぶ場合(20日以内が期限!)
| 項目 | 申請先 | 必要なもの(核となる書類) |
| 申請先 | 以前加入していた健康保険組合、または協会けんぽ支部 | 任意継続被保険者資格取得申出書 |
| 主な添付書類 | 退職日の確認ができる書類(離職票の写しなど)、扶養家族の収入証明(扶養する場合) | |
| 注意点 | 申請期限(20日以内)に間に合わせることが最優先です。 |
【パターンB】国民健康保険を選ぶ場合(退職後14日以内が目安)
| 項目 | 申請先 | 必要なもの(核となる書類) |
| 申請先 | お住まいの市区町村役場の窓口(国保担当課) | 健康保険の資格喪失証明書(会社からもらう) |
| 主な添付書類 | 離職票や退職証明書、本人確認書類(マイナンバーカードなど)、印鑑 | |
| 注意点 | 国保への加入手続きの期限は退職日から14日以内です。期限が短いので、会社から資格喪失証明書を受け取り次第、早めに役場へ行きましょう。 |
まとめ:最終確認と75歳以降の安心
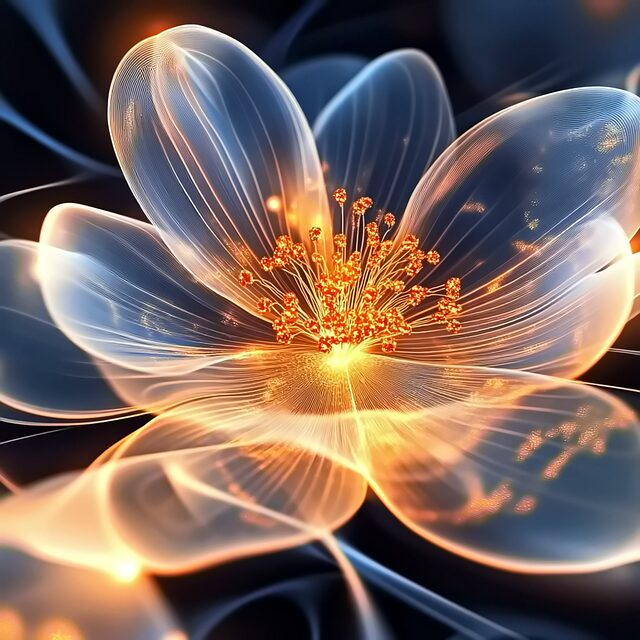
退職後の健康保険の選び方は、「お金(金額)」「時間(20日以内という期限)」「理由(自己都合か会社都合か)」の3つを総合的に判断することが大切です。
【最終判断】「任意継続」か「国保」か、再チェック!
| チェック項目 | 判定結果 |
| 1. 給料が高く、扶養家族がいるか? | YES ⇒ 任意継続が有利 |
| 2. 会社都合や倒産で退職したか? | YES ⇒ 国保+割引制度が有利 |
| 3. 任意継続の申請期限(20日以内)に間に合うか? | NO ⇒ 国保を選ぶしかありません |
75歳以降の心配はいりません!

「この保険に2年間入った後、75歳になったらどうなるの?」というご不安もあるかもしれませんね。ご安心ください。
任意継続の被保険者期間が2年間で終了した後、あなたがお住まいの自治体の国民健康保険に加入することになります。
そして、75歳になると、自動的に「後期高齢者医療制度」に切り替わります。この75歳になる時点では、基本的にあなたから役所に特別な手続きをする必要はありません。
私自身が年間18万円の節約に成功したように、あなたもこの記事の情報とチェックリストを使えば、必ず最適な選択ができ、大きな経済的なメリットを手にできるはずです。まずは「20日の期限」を念頭に置き、お近くの窓口に相談してみましょう。
◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。
にほんブログ村 |
シニアライフランキング |
素敵な買い物が出来る、通販サイトです。シニアに喜ばれる商品が豊富です。