「歯周病なんて口の中だけ」は誤解? 糖尿病との意外な関連性
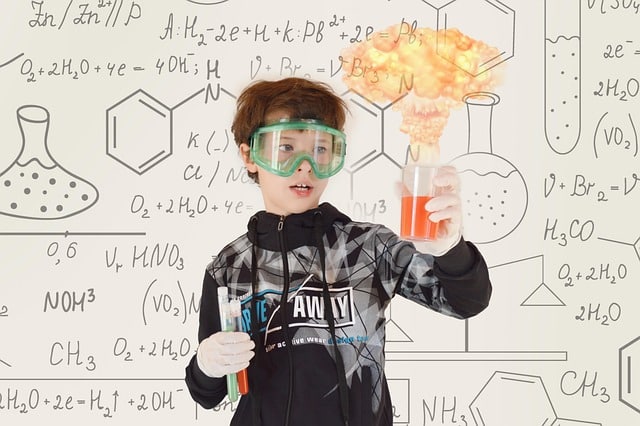
「最近、どうも歯ぐきが腫れやすい…」「糖尿病の数値がなかなか安定しない…」とお悩みではありませんか?実は、一見関係なさそうに見えるその二つの悩みは、お口の中の歯周病が原因かもしれません。

この記事を読み終える頃には、以下の疑問や悩みを解決し、明日から実践できるヒントを得られるでしょう。
- 糖尿病と歯周病がどう関係しているのか知りたい
- 自分の口の中の歯周病サインに気づきたい
- 血糖値を安定させるための効果的なケア方法が知りたい
- 歯周病治療で本当に血糖値が良くなるのか知りたい
歯周病とは、歯の汚れによって細菌が増え、周辺の歯肉に炎症を起こし、自覚症状がないまま進行すると、歯を支える骨が破壊され、最終的に歯が抜けてしまう病気です。これだけでも、食物を正しく咀嚼することを妨げる恐ろしい病気ですが、更にその細菌が体内に入ったときインスリンの働きを阻害して血糖値が上昇し、糖尿病の原因となっているという記事が 2017.7.29読売新聞朝刊 に記載されています。
記事によると、歯周病は感染症で、病気を起こす細菌が体内に入ったとき、体は菌を排除しようと強い炎症を起こす。炎症を起こす物質がたくさん作られると、血糖を下げるインスリンの働きを邪魔することによって糖尿病になるリスクを上げるということだそうです。
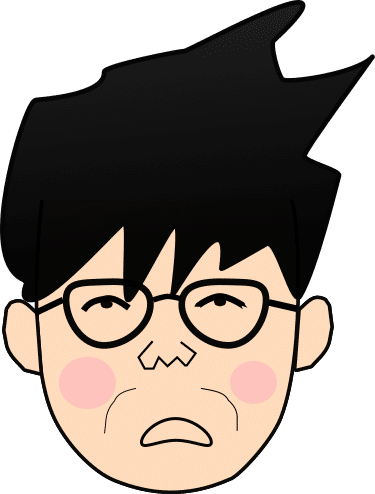
以前、千葉大学の大学病院で手術を行う患者に対して、施術前に歯の専門家による腔内のケアが行われ、行っていなかった時と比べると術後の経過が非常に良いとの記事が読売新聞に掲載されました。糖尿病に限らず、腔内ケアは健康を維持するためには、とても重要ですね。
厚生労働省資料、【口腔機能管理等による効果と医科歯科連携が効果的に機能している事例 】で、千葉大学の腔内ケアと手術の関連による研究結果が取り上げられています。
「歯周病なんて、ただの口の中の病気でしょ?」そう思われる方も多いでしょう。しかし、糖尿病と歯周病の相互関係について、日本糖尿病学会と日本歯周病学会が共同で作成した委員会報告、日本糖尿病学会と日本歯周病学会による最新の研究報告でも、歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼし合うことが報告されています。
又、最近の研究では、歯ぐきの炎症を引き起こす歯周病菌が体内に慢性的な炎症をもたらし、老化やフレイル(加齢に伴う機能低下)のリスクを高める可能性が示されています。歯周病は「歯の病気」だけでなく、全身の健康や老化プロセスにも影響する炎症性疾患と考えられるため、口腔ケアは健康寿命を保つうえでも重要です。
【慶応義塾大学病院】歯周病が引き起こす多臓器のフレイル~炎症性老化による全身への影響を解明
このブログ記事は、私自身が「歯周病と糖尿病の関係」について調べ、理解した内容を、専門家ではない読者の皆さまにわかりやすくお伝えするために執筆しました。この記事を通じて、あなたの不安を少しでも和らげ、血糖値を安定させるためのヒントを見つけていただければ幸いです。
歯周病と糖尿病の相互関係|負のスパイラルを断ち切る鍵

1. 歯周病が血糖値を上昇させるメカニズム
歯周病は、歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)に溜まった細菌が、歯ぐきに炎症を起こす病気です。この歯周病菌が歯ぐきから血管内に入り込むと、全身に炎症反応が起こり、炎症性物質が分泌されます。
この炎症性物質が、血糖値を下げる唯一のホルモンであるインスリンの働きを妨げる作用を持つため、血糖値が上がってしまうのです。これがインスリン抵抗性と呼ばれる状態で、糖尿病をさらに悪化させる原因となります。
2. 逆に、糖尿病が歯周病を悪化させる仕組み
血糖値が高い状態が続くと、全身の血管にダメージが蓄積し、歯ぐきへの血流も悪化します。これにより、歯ぐきに必要な栄養や酸素が届きにくくなり、細菌と戦う免疫力も低下するため、歯周病菌が繁殖しやすくなります。このように、歯周病と糖尿病は、一方が悪化するともう一方も悪化するという「負のスパイラル」の関係にあるのです。
この負のスパイラルについては、静岡県歯科医師会が「糖尿病」のサイトで、解りやすく説明されています。
歯周病治療がもたらす驚くべき血糖値改善効果
多くの研究で、歯周病の治療を行うことで、血糖値が改善する可能性が示唆されています。歯周病治療によって口の中の炎症が抑えられると、全身の炎症反応も緩和され、インスリンが効きやすい状態になるためです。
特に、歯周病治療により血糖コントロールの指標であるHbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)が約0.4%改善するという研究結果も報告されており、その効果の大きさが注目されています。
この研究については、日本糖尿病学会と日本歯周病学会が合同で作成した「糖尿病患者に対する歯周治療ガイドライン」で詳しく説明されています。
糖尿病患者が知っておくべき歯周病のサインとセルフケア

1. 自分の口の中をチェック!歯周病の初期サインを見逃さない
糖尿病の治療には、毎日の丁寧な口腔ケアが欠かせません。以下の項目に当てはまる場合は、歯周病が進行している可能性があります。
- 朝起きた時に口の中がネバつく
- 歯みがきの時に歯ぐきから出血する
- 硬いものを食べた時に違和感がある
- 歯ぐきがむず痒い、または腫れている

これらのサインを見逃さず、早めに歯科医院に相談することが大切です。
2. 血糖値を安定させるための効果的な口腔ケア
次の日本医師会のホームページで、歯周病を予防し、又はその進行を抑えるために効果的な正しい歯磨きの方法が、公開されています。

やり方は難しくないので、今日から実践されることをお勧めします。ちなみに私は、数年前からこの方法で歯を磨いています。
又、朝の歯磨きは起床してすぐ、食事をとる前に行うのがベストです。歯周病菌が口内で一番活発に動き回っているのがこの起床してすぐの時です。これも、歯周病菌を食事と一緒に体内に取り込まない為のテクニックの一つです。
もりや歯科医院のブログ記事、「歯周病にも効果あり。朝の歯みがきについて」で、睡眠中に唾液の分泌が減ることで細菌が増殖し、起床直後には細菌でいっぱいになっているため、まず歯磨きをして細菌をリセットすることが推奨されています。
糖尿病患者のための具体的なアクションプラン

1. 主治医との連携が不可欠
歯科医院での治療を始める前に、必ずかかりつけの歯科医と糖尿病の主治医に相談し、歯科治療の予定を共有しましょう。主治医に事前に伝えておくことで、治療中の血糖値管理や薬の調整など、より安全で効果的な治療計画を立てることができます。
2. 歯科受診時に伝えるべきこと
歯科医院を受診する際は、必ず以下の点を歯科医に伝えてください。
- 糖尿病であること
- 糖尿病の服薬状況やインスリン注射の有無
- HbA1cの数値や血糖コントロールの状態
- その他の持病や服用中の薬
これらの情報があることで、歯科医はあなたに合った最適な治療法を判断することができます。
まずは、お近くの歯科医院で相談してみませんか?
この記事を読んでもし少しでも不安に感じたり、ご自身の口腔内の状態が気になったりした場合は、一度歯科医院で相談してみることを強くお勧めします。
歯周病は自覚症状がないまま進行することが多いため、早期発見・早期治療が何よりも大切です。歯科医師に相談することで、あなたに合った最適なケア方法が見つかるはずです。
まとめ:今日から始める健康習慣が血糖値を守る

「歯が痛くなってから歯医者に行く」のではなく、3ヶ月〜半年に一度の定期的な歯科検診を習慣にしましょう。

早期発見・早期治療が、歯周病の進行を防ぎ、結果として糖尿病のコントロールにも繋がります。
◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。
にほんブログ村 |
シニアライフランキング |


