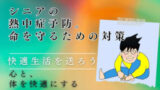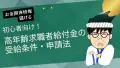この記事を読むと以下の疑問が解決できます。

◇ ブログランキングに参加しています。応援して頂ければ嬉しいです。
にほんブログ村 |
シニアライフランキング |
今年の夏も暑い日が続きそうですね。
「エアコンの電気代が気になるけど、熱中症も怖い…」と感じている高齢者の方や、そのご家族もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事を読むと、以下の疑問や問題が解決できます。
- 熱中症の心配と電気代の悩みが減ります。
- 自分に合った快適な室温設定がわかります。
- エアコンの、お財布に優しい上手な使い方がわかります。
- 省エネで安心なエアコン選びのポイントがわかります。
- 家族がエアコンを使ってくれない場合の伝え方を知り、円満な解決につながります。

この記事では、高齢者の方が安心してエアコンを使い、快適に夏を過ごせるための節約術と健康管理のコツを分かりやすくご紹介します。
なぜ高齢者のエアコン冷房節約が重要なのでしょう?

熱中症のリスクとエアコン使用の現状
日本の夏は年々暑くなり、特に高齢者の方にとって熱中症は命に関わる深刻な問題です。体温調節機能の低下や水分量の減少により、暑さを感じにくくなるため、熱中症で救急搬送される方の約半数を高齢者が占めています。
[参考]総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」
![]総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」資料(概要)](https://takuchanbrog.com/wp-content/uploads/2025/07/heatstroke_nenpou_r6-1.png)
![]総務省消防庁「熱中症による救急搬送状況」資料(内訳) 年齢区分別の救急搬送人員](https://takuchanbrog.com/wp-content/uploads/2025/07/heatstroke_nenpou_r6-2.png)
しかし、「電気代がもったいない」「体に良くない」という理由から、エアコンの使用をためらう方が少なくありません。熱中症は進行が早く、意識障害などを引き起こす可能性もあるため、予防が何よりも大切です。
環境省も熱中症予防のためにエアコンの適切な使用を推奨しています。特に、夜間の熱中症も多いため、寝室でのエアコン使用は欠かせません。
高齢者がエアコンを上手に使い、熱中症のリスクを減らすことは、健康で快適な生活を送る上でとても大切です。電気代の心配は確かにありますが、賢くエアコンを使えば、費用を抑えながら健康を守ることができます。
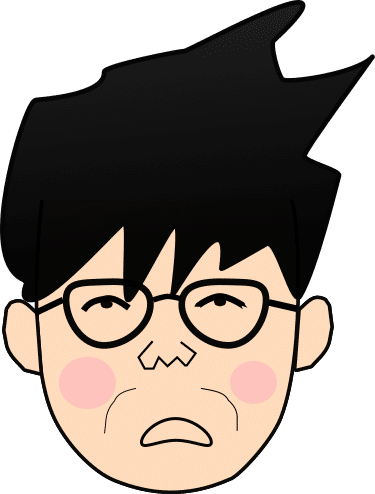
熱中症に関しては、こちらの記事も参考にしてください。
電気代の心配からエアコンを我慢する問題
「エアコンを使いたいけれど、電気代が心配…」これは多くの方が抱える悩みでしょう。年金生活の中で電気代が上がるのは大きな負担です。そのため、夏場にエアコンの使用を我慢してしまうケースも少なくありません。
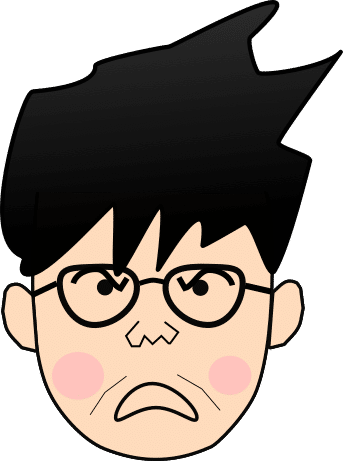
例えば、「昼間は扇風機だけで過ごす」という方もいますが、これが原因で軽度の熱中症になりかけた例もあります。電気代の節約は大切ですが、健康を損ねてしまっては意味がありません。
「エアコンは電気代が高い」というイメージがあるかもしれませんが、最近のエアコンは省エネ性能が格段に上がっています。古いエアコンを使い続けるよりも、新しいエアコンに買い替える方が電気代が安くなることもあります。また、少しの工夫で電気代を大きく減らすことも可能です。例えば、設定温度を少し見直したり、扇風機と併用したりするだけでも効果があります。

電気代を理由にエアコンを我慢し、熱中症の危険にさらされるのは避けたいことです。安心して快適に夏を過ごせるよう、電気代を賢く節約しながらエアコンを使う方法を知ることが大切です。
今日からできる!エアコン冷房の賢い節約術【基本編】

室温設定の最適化:エアコンの快適温度と節約のコツ
エアコンの室温、何度に設定していますか? 環境省が推奨する「28℃」はあくまで目安です。大切なのは、ご自身が「快適だと感じる温度」を見つけることです。
湿度の高い日や風がない部屋では、28℃でも暑く感じる場合があります。高齢者の方は体感温度が異なることも多いため、無理に28℃にこだわる必要はありません。
- まずは28℃から始め、少しずつ調整する: 暑ければ27℃、26℃と1℃ずつ下げて、快適な温度を見つけましょう。
- 「弱冷房除湿」を活用する: 温度を下げるだけでなく、湿度を下げることでも快適に感じられます。「弱冷房除湿」は電気代が安いためおすすめです。
- 温度より風量で調節する: エアコンの温度を1度下げるよりも、風量を強くする方が電気代はかかりません。まずは風量で調整を試みましょう。
- 扇風機やサーキュレーターと併用する: 室内の空気を循環させることで、体感温度が下がり、エアコンの設定温度を上げても快適に過ごせます(詳しくは後述)。
これらの工夫で、無理なく快適な室温を保ちながら電気代も節約できます。
フィルター掃除は2週間に1度が鉄則:電気代節約の基本

エアコンのフィルター掃除は、2週間に1度行うのが理想です。これは、電気代節約にとても重要なポイントです。
フィルターにホコリが溜まると、エアコンは設定温度にするために余分な電力を使うことになります。これにより、消費電力が約5%〜10%も増えると言われています。年間で数千円、場合によっては1万円以上の電気代の無駄につながります。
フィルター掃除は難しくありません。多くのエアコンは、前面パネルを開ければ簡単にフィルターを取り外せます。ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いしましょう。水洗いした場合は、しっかり乾かしてから取り付けてください。
たった数分の作業で、電気代の節約とエアコンから出る空気の清潔さを保ち、健康にもつながります。ぜひ今日から2週間に1度のフィルター掃除を習慣にしてみてください。
室外機周りの環境を整えるコツ

エアコンの節約術は、室内だけでなく室外機周りの環境を整えることも大切です。室外機は熱を外に排出する役割があるため、周囲に物を置かず、直射日光が当たらないように工夫しましょう。
室外機周りの温度が高いと、エアコンはより多くの電力を使って熱を排出しようとし、電気代が余計にかかってしまいます。
- 直射日光を避ける: 室外機に直射日光が当たると、室外機自体の温度が上昇し、熱の排出効率が低下します。簡単な対策としては、ホームセンターなどで手軽に購入できる室外機用の日よけやエアコン室外機遮熱シートを設置して直射日光を避けることが有効です。ただし、室外機を完全に覆うカバーは熱がこもり、逆効果になることがあります。
- 周囲に物を置かない: 室外機の周りに物があると、熱の排出が妨げられます。吸気口や排気口の周りには、20〜30cm以上のスペースを空けるようにしましょう。
- 室外機の裏を掃除する: 室外機の側面や裏にある「フィン」という部分が汚れていると、効率が悪くなります。掃除機や歯ブラシで優しくゴミを取り除きましょう。
- 室外機を冷やす: 周囲に打ち水をするのも効果的です。直接水をかけるのは故障の原因になるため避けましょう。
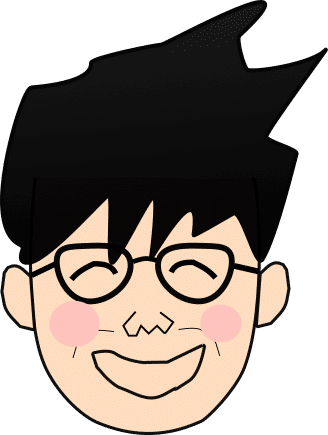
これらの対策で、室外機が効率よく働き、電気代の無駄を抑えることができます。
タイマー機能の活用

就寝時や外出時に便利なのがエアコンのタイマー機能です。上手に活用することで、無駄な運転を避け、電気代を節約できます。
- おやすみタイマー: 寝苦しい夜でも、寝入りばなの数時間だけ冷房を使い、その後は自動で停止するように設定できます。タイマーが切れた後も冷気が残るため、朝まで快適に過ごせる場合が多いです。
- おはようタイマー: 朝起きる少し前に冷房が自動でスタートするように設定すれば、暑くて目覚めることなく、快適な室温で一日を始めることができます。
タイマーを賢く使うことで、必要な時だけ冷房を使い、不必要な時間帯の電気代を削減できます。
就寝時のモード選択(おやすみモードなど)
多くのエアコンには、就寝時の快適性を高めるための「おやすみモード」や「快眠モード」といった機能が搭載されています。これらのモードを積極的に活用しましょう。
おやすみモードは、設定温度を緩やかに変化させたり、風量を自動で調整したりすることで、寝ている間の体の冷えすぎを防ぎます。また、静音運転に切り替わることも多く、睡眠の質を高める効果も期待できます。
冷えすぎを防ぎ、電気代も節約できるため、ぜひリモコンの表示を確認し、活用してみてください。
さらに効果的!エアコン冷房の応用節約テクニック
扇風機・サーキュレーターの併用で冷気を循環

エアコンと扇風機やサーキュレーターの併用は、電気代節約に非常に効果的なテクニックです。エアコンの設定温度を無理に下げなくても、部屋全体を効率的に冷やし、快適に過ごせます。
エアコンから出る冷たい空気は床付近に溜まりやすいため、エアコンだけだと部屋に温度ムラができがちです。扇風機やサーキュレーターは、この空気をかき混ぜて部屋全体に循環させる役割があります。
- エアコンの対角線上に設置する: 冷たい空気を効率よく行き渡らせるため、扇風機やサーキュレーターをエアコンの風が来る方向に向けて設置すると効果的です。
- 上向きに送風する: 首を上向きにして天井に向けて風を送ると、天井に溜まった暖かい空気を混ぜ、冷気を部屋全体に広げやすくなります。
- 風量は「弱」や「微」で十分: 強風でなくても、空気をゆっくり循環させるだけで十分に効果があります。
扇風機やサーキュレーターを併用することで、エアコンの設定温度を1〜2℃上げても快適に過ごせるようになり、その分電気代を大幅に節約できます。
短時間の外出は「つけっぱなし」がお得な理由
「ちょっとコンビニに行くだけだから、エアコンを消していこう」。短時間の外出であれば、実は「つけっぱなし」の方が電気代がお得になることが多いのをご存知でしょうか。
エアコンは、運転を止めてから再び動かす際に最も多くの電力を消費します。暑い部屋を一気に設定温度まで下げる「立ち上げ時」に、一番大きなエネルギーが必要になるからです。一度設定温度に達すれば、その温度を維持するための電力はぐっと少なくなります。
電力会社のシミュレーションでは、30分程度の外出なら、つけっぱなしの方が電気代が安くなる傾向があるとされています。例えば、ダイキン工業の調査では、外気温31℃の日にエアコン(2.2kWクラス)を設定温度26℃で連続運転した場合と、30分後に一度停止し再運転した場合を比較すると、30分程度の外出であればつけっぱなしの方が消費電力が少ないという結果が出ています。
[参考]ダイキン工業「エアコンはつけっぱなしがお得?」:
エアコンを消して外出すると、その間に室温が上がり、帰宅後に再び電源を入れた際に、また「立ち上げ時」の大きな電力が必要になるためです。
この「つけっぱなし」は、急激な室温変化による体への負担を減らす効果もあります。暑い部屋から急に冷たい部屋に入ると、体調を崩すリスクも考えられます。常に快適な室温を保つことで、身体への負担を減らしながら電気代も抑えられる、一石二鳥の対策です。
湿度のコントロールで体感温度を下げる方法
夏に「蒸し暑い」と感じるのは、気温だけでなく湿度が高いことが大きな原因です。エアコンの冷房だけでなく、除湿機能を上手に活用して湿度をコントロールすることで、少ない電力で快適に過ごせます。
人間は汗をかき、その汗が蒸発することで体温を下げています。しかし、湿度が高いと汗が蒸発しにくくなり、体がベタベタして不快に感じるため、室温が低くても「蒸し暑い」と感じてしまうのです。
エアコンの除湿機能には主に2つのタイプがあります。
- 弱冷房除湿: 冷房の弱いモードで除湿します。電気代が安いため、おすすめです。
- 再熱除湿: 湿気を取り除いた空気を再び温めて室内に戻す機能です。室温を下げずに湿度だけを下げられるため、梅雨時や冷えすぎを防ぎたい場合に便利ですが、消費電力はやや高めです。
まずは弱冷房除湿を試してみてください。設定温度をいつもより少し高め(例えば28℃)にして弱冷房除湿を運転すると、湿度が下がり、快適に感じられるはずです。室内に湿度計を置き、快適な湿度(50%〜60%程度が目安)を探してみるのも良いでしょう。
湿度を下げることで、汗が蒸発しやすくなり、肌がサラッと快適になります。これにより、エアコンの設定温度を高く保ちながらも快適に過ごせ、電気代の節約につながります。
その他の使い方に関する節約テクニック
- 送風機能の活用: 帰宅して部屋に熱気がこもっている場合、すぐにエアコンをつけるのではなく、まず窓を開けて熱気を追い出しましょう。この時、エアコンの送風機能を使うとスムーズに換気ができます。送風機能は1時間あたり0.5円程度と電気代が非常に安いため、熱気を逃がしてから冷房運転に切り替えることで節電になります。
高齢者向け!冷えすぎを防ぐ快適冷房の工夫
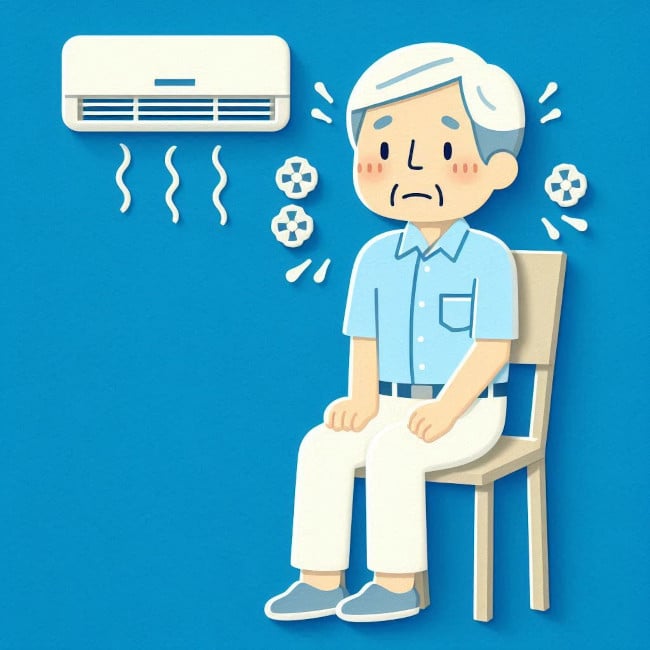
風向きと風量の自動設定を活用する
エアコンの冷たい風が直接体に当たると、体が冷えすぎたり、体調を崩したりすることがあります。特に高齢者の方は、体への負担が大きいため、エアコンの風向きと風量を「自動設定」にすることをおすすめします。
自動設定にすると、エアコンが室温や外気温などを感知し、最も効率的で快適な風量と風向きを自動で判断してくれます。例えば、設定温度になるまでは強風で一気に冷やし、その後は微風で室温を維持するといった賢い運転をしてくれます。
また、冷たい空気が床に沿って広がるように、ルーバーを下向きに設定し、広い範囲に風を送るように自動で制御されることが多いです。これにより、冷気が部屋全体に効率よく行き渡り、特定の場所に冷風が集中するのを防げます。
エアコンのリモコンにある「自動」ボタンを押すだけで簡単に設定できます。もし自動設定がない場合は、「弱」や「微」などの低い風量設定を選び、風向きは冷気が直接体に当たらないように、天井方向や壁方向にルーバーを向けると良いでしょう。
エアコンの風が直接当たらない工夫
エアコンの風が直接体に当たると、肌の乾燥や体の冷えすぎ、肩こりや頭痛の原因になることもあります。特に高齢者の方は、体温調節機能が低下しているため、風が直接当たらないように工夫することが大切です。
- ルーバーを水平にする: 冷たい空気は床にたまる性質があるため、風向きを下向きにすると温度ムラができやすくなります。ルーバーを水平にすると、部屋全体を効率的に冷やすことができます。
- 家具の配置を見直す: ソファやベッドをエアコンの直下に置かないようにするなど、風の通り道から外れる位置に移動させましょう。
- エアコン風よけカバーの活用: 市販の風よけカバーを取り付けると、風の流れをコントロールし、直接風が当たるのを防げます。
- 扇風機やサーキュレーターの活用: エアコンの対角線上に置いて上向きに運転することで、冷気を部屋全体に循環させ、直接風に当たる必要を減らせます。
これらの工夫で、冷えすぎによる体調不良を防ぎ、快適な室内環境を保つことができます。
部屋の断熱性を高める簡単アイデア
エアコンを使ってもなかなか部屋が冷えなかったり、すぐに温度が上がってしまったりするのは、部屋の断熱性が低いことが原因かもしれません。特に窓は熱の出入りが最も大きい場所です。
大掛かりなリフォームをしなくても、手軽にできる断熱対策はたくさんあります。
- 遮光カーテンや遮熱カーテンを活用する: 日中の日差しが強い時間帯は、しっかりとカーテンを閉めることで、室温の上昇を大幅に抑えることができます。
- 窓に断熱シートを貼る: 窓ガラスに貼るタイプの断熱シートも有効です。特に西日が当たる窓に貼ると効果を実感しやすいでしょう。
- 隙間テープで窓やドアの隙間を塞ぐ: 古い窓やドアの隙間から冷気が逃げたり、熱気が侵入したりすることがあります。隙間テープを貼ることで断熱性を高められます。
- 簡易的な内窓の設置: DIYで設置できる簡易的な内窓も販売されています。既存の窓の内側にもう一つ窓を設けることで、断熱効果が高まります。

これらの対策は、冷房だけでなく冬の暖房効率も高めるため、年間を通して省エネ効果が期待できます。室温を安定させることで、健康維持にもつながります。
最新エアコン機能の活用と選び方

高齢者におすすめの省エネ機能(AI、見守り機能など)
最近のエアコンには、快適性や安心感を高める様々な機能が搭載されています。特に高齢者の方にとっては、AI機能や見守り機能、人感センサーなどが省エネと健康をサポートしてくれます。
- AI(人工知能)機能: 部屋の状況や人の活動量などを学習し、最も効率的かつ快適な運転モードを自動で判断してくれます。自分で細かく設定しなくても、無駄な電力消費を抑えながら快適さを保てます。
- 代表例: パナソニックの「エオリアAI」は、AIが室温や日差し、人の活動量を検知し、自動で運転を最適化します。ダイキンの「AI快適自動運転」も同様に、部屋の状況に応じて最適な温度・湿度を自動でコントロールします。
- 見守り機能: 室温や湿度を感知し、熱中症のリスクが高まるとアラートを出したり、自動で運転を開始したりする機能です。離れて暮らす家族が、アプリでエアコンの状態を確認できるモデルもあり、高齢者の一人暮らしでの安心感を高めます。
- 代表例: シャープの「見守り機能」や、富士通ゼネラルの「高温みまもり」などが該当します。
- 人感センサー(不在検知機能): 人の動きを感知し、部屋に人がいないことを検知すると、自動で運転を弱めたり停止したりします。これにより、消し忘れによる無駄な電力消費を防ぎ、人が戻ると再び運転を再開します。
- 代表例: 東芝の「人感センサー」や、日立の「くらしカメラAI」などがあります。
これらの機能は、初期費用が高く感じるかもしれませんが、長期的に見れば電気代の節約につながり、何よりも健康と安心を買う投資と考えることができます。
エアコン買い替え時にチェックすべき節約ポイント
エアコンの買い替えは大きな買い物だからこそ、長期的に見て電気代の節約につながる賢い選択をすることが重要です。以下の3つのポイントをチェックしましょう。
- 省エネ性能(APF/通年エネルギー消費効率): エアコンの省エネ性能は、APF(通年エネルギー消費効率)という数値で示されます。数値が大きいほど省エネ性が高いことを意味します。エアコンの省エネ性能は年々向上しており、古いエアコンよりも新しいものに買い替える方が電気代が安くなることが多いため、長く使うなら省エネ性能に優れたモデルを選びましょう。
- 部屋の広さに合った能力(畳数表示): カタログに記載されている「○畳用」という畳数表示は重要です。部屋の広さに対して能力が小さすぎると、常にフル稼働することになり、かえって電気代が高くなります。逆に大きすぎても初期費用が無駄になります。一般的には、表示されている畳数より少し大きめの能力を選ぶと効率が良いとされています。
- 除湿機能の種類: 前述の通り、湿度コントロールは節電につながります。「再熱除湿」機能など、室温を下げずに湿度だけを下げられる高機能な除湿機能が搭載されているかどうかもチェックすると良いでしょう。
- 代表例: ダイキンには「さらら除湿」という、温度を下げすぎずに湿度をしっかり取り除く高機能な除湿機能があります。三菱電機のエアコンにも「ハイブリッド運転」など、快適性と省エネを両立する機能が搭載されています。
これらのポイントをしっかり確認して賢く選べば、毎月の電気代を抑え、快適な暮らしを手に入れるための良い投資となるでしょう。
Q&A:高齢者のエアコン冷房節約に関するよくある疑問
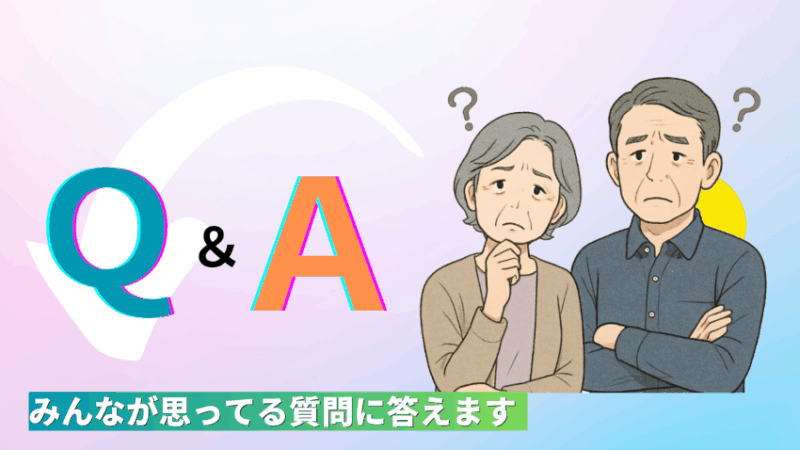
「冷房病」が心配な場合の対策は?
夏にエアコンを使うと、体がだるくなったり、頭が痛くなったりして「冷房病」を心配する方もいるかもしれません。特に高齢者の方は体温調節機能が低下しているため、冷えすぎは避けたいところですが、適切な使い方をすれば、冷房病の心配なく快適に過ごせます。
冷房病の主な原因は、冷えすぎと自律神経の乱れです。設定温度が低すぎたり、風が直接体に当たったりすることで血行が悪くなり、体調不良につながります。
具体的な対策は以下の通りです。
- 室温設定を見直す: 28℃を目安に、ご自身が快適だと感じる温度を探し、無理に下げすぎないようにしましょう。除湿機能の活用も効果的です。
- 風向きと風量を調整する: 風が直接体に当たらないように、ルーバーを上向きや水平にして、部屋全体に冷気を循環させましょう。風量も「自動」や「弱」がおすすめです。
- 羽織るものやひざ掛けを活用する: 冷えやすい首元、お腹、足元などを冷やさないように、薄手のカーディガンやストール、ひざ掛けなどを使いましょう。
- こまめな水分補給: 冷房の効いた部屋でも体は乾燥します。意識して水分を摂りましょう。冷たい飲み物だけでなく、常温の水やお茶も取り入れると良いです。
- 軽い運動や入浴で血行促進: 体が冷えがちな場合は、軽いストレッチやウォーキング、ぬるめのお風呂に浸かるなどで血行を促進しましょう。
無理にエアコンを我慢して熱中症になるよりも、上手にエアコンを活用し、これらの対策を取り入れることが大切です。
家族がエアコンを使ってくれない時の伝え方
「暑いのに、おじいちゃん(おばあちゃん)が電気代を気にしてエアコンを使ってくれない…」という悩みはよく聞かれます。高齢者の方は、長年の習慣や節約意識からエアコンの使用をためらいがちです。しかし、熱中症は命に関わるため、理解を促し、エアコンを使ってもらうことが不可欠です。
頭ごなしに使うよう促すのではなく、相手の気持ちに寄り添い、具体的なメリットを分かりやすく伝えることが重要です。
- 熱中症の具体的なリスクを伝える(脅かすのではなく、事実として): 「体調を崩して病院に行く方が、かえってお金がかかるかもしれないよ」と、経済的な観点からもエアコン使用の必要性を伝えましょう。
- 最新エアコンの省エネ性能を伝える: 「昔のエアコンと違って、今のエアコンはすごく省エネになっているんだよ。つけっぱなしの方がお得な場合もあるんだ」と、最新の技術で電気代の心配が減ること伝えましょう。
- 快適さ・安心感を強調する: 「涼しい部屋でゆっくり過ごす方が、体も楽だし、夜もぐっすり眠れるよ。おじいちゃん(おばあちゃん)が快適に過ごしてくれるのが、私たち家族にとって一番の安心だから」と、本人の快適さや家族の安心につながることを伝えましょう。
- 具体的な節約術を一緒に実践する: 「フィルター掃除も一緒にやってみない?」「扇風機と併用するともっと涼しくなるんだって」など、具体的な節約術を一緒に試すことを提案し、慣れてもらいましょう。
- 「見守り」の姿勢を示す: 「もし暑いと感じたら、遠慮なくエアコンつけてね。何かあったらすぐ連絡してね」と伝え、安心感を与えましょう。室温計を設置して目安を共有するのも良い方法です。
大切なのは、決して高圧的にならず、相手の健康を心から気遣う気持ちを伝えることです。
エアコンをつけっぱなしにした場合の具体的な電気料金の目安は?
エアコンをつけっぱなしにした方が電気代がお得になるケースがあるのは先ほど説明しましたが、具体的にどれくらいの電気料金がかかるのか気になる方もいるでしょう。
一般的な6畳用のエアコン(期間消費電力量500kWh/年程度)を冷房運転で28℃設定にした場合、1日24時間つけっぱなしにした場合の電気代は、1時間あたり約5円〜10円が目安となります(電力会社や契約プラン、外気温などによって変動します)。
つまり、1日つけっぱなしにしても、約120円〜240円程度で快適な室温を保てる計算です。 これは、頻繁にオンオフを繰り返して立ち上げ時の大きな電力を消費するよりも、結果的に安くなる可能性があるということです。
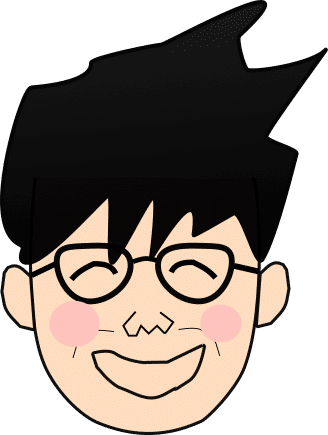
もちろん、これはあくまで目安であり、お使いのエアコンの機種や年式、設定温度、室外機の環境、電力会社の料金プランなどによって大きく変わります。しかし、この金額を知ることで、「電気代が高くなる」という漠然とした不安が和らぎ、安心してエアコンを使えるようになるのではないでしょうか。
終わりに:賢く節約して健康で快適な夏を!

今回は、高齢者の方が夏の暑さを快適に、そして健康的に乗り切るためのエアコンの賢い使い方と節約術をご紹介しました。

これらの知識と工夫を身につけることで、電気代の心配を最小限に抑えながら、安全で快適な夏を過ごすことができるはずです。今年の夏こそ、賢くエアコンを活用して、健やかな毎日を送ってください。